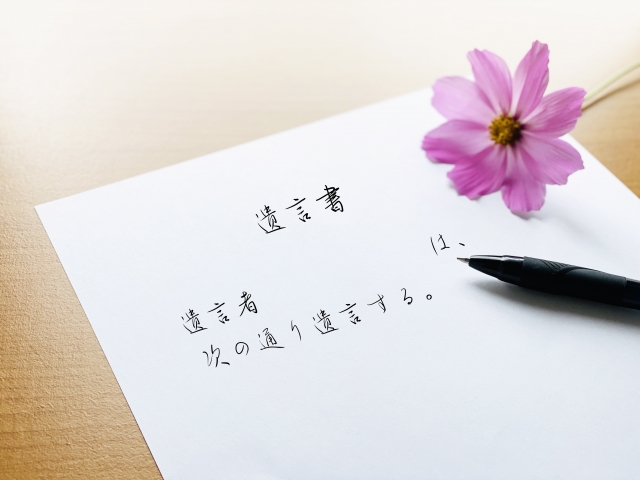遺言とは
遺言とは、一定の方式に従った遺言をする方の死後の法律関係を定める最終の意思表示をいいます。法律に定められた方法・ルールで行わないと無効となりますので、ルールを定めた「民法」をしっかりと確認することが必要です。
では、一定の方式とはどのようなものか、遺言はまず平常時に行う普通方式と、緊急時に行う特別方式に分かれます。このうち特別方式については、病気・事故の際などに用いられるものですので紹介を省きます。私たちが日常の場面で遺言と認識しているものは「普通遺言」の方となりますので、今回はこの「普通遺言」のうち「自筆証書遺言」をご紹介します。
自筆証書遺言とは〜メリット・デメリット
自筆証書遺言とは、名称から想像されるとおり、自ら筆記(自筆)をするものです。
自分で書いて作成するものですから、基本的に費用がかからず比較的容易にできるというメリットがあります。一方、第三者のチェック・アドバイスがないと民法のルールから外れた内容となって無効となる可能性が高まります。また、保管も原則として自分で行うため、紛失・偽造・変造・隠匿・破棄のおそれが他の方式に比べて高いと言わざるを得ません。ただし、この保管については、令和2年7月施行の遺言書保管法の改正により、法務局において自筆証書遺言の保管が可能となりましたので、上記のおそれは若干緩和されています。
また、自筆証書遺言は、相続開始後(遺言をした人の死亡後)に、家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。これには、通常1ヶ月程度の期間を要しますので、その分相続財産の整理にも期間を要することとなります。なお、この点についても先にご紹介した法務局における自筆証書遺言の保管を利用すれば、検認規定が除外されます。制度利用を前提とするものの、以前に比べると保管以後のデメリットが緩和されている状況です。
自筆証書の作成のはじまり
では自筆証書遺言はどのようにすればよいか、作成の流れをご紹介します。なお、この流れは弊所での基本的なもので、場合によって前後・有無の相違があります。
(1) 人的調査〜相続関係図の作成
遺言をする人を中心とした人間関係=相続関係を整理します。自筆証書遺言の場合、遺言をする人の想いを表す要素が強い傾向があるため、法定相続に即した情報は不要とも思えますが、法定どおりの場合と自らの考えに沿った場合の違いを認識することで、遺言をする必要性の再確認ができます。そのためには、「遺言をする人の出生から現在までの戸籍謄本」と「推定相続人の戸籍謄本」を入手して、相続関係説明図を作成します。
(2) 財産調査〜財産目録の作成
遺言は、残された人への想いをつづりますが、その中心となるものは「財産」です。したがって、遺言をする人の財産に関する情報をまとめる必要があります。財産は、①不動産、②金融資産、③動産に分類されますが、①については役所・役場からの固定資産税納税通知書をもとに登記所から登記事項証明書を取得します。②については、現金・預金・有価証券などが該当しますので、それらの残高をまずは直近の残高を通帳等により確認します。そして、③については、自動車の車検証等で確認することができるものもありますが、主に口頭でヒアリングをし、一覧的に整理していきます。なお、財産については、相続税が気になるところですので、場合によっては専門家である税理士への相談を必要とします。
以上、財産調査によって情報を集め、財産目録を作成します。
全文の作成〜要件チェック
(1) 文案の作成
自筆証書遺言は、全文(財産目録を除く)を自筆する必要がありますが、いきなり全文を書くことは難しく、途中で内容を変更・修正する場合の方式も厳格に定められていますので、まずはパソコンなどで原案を作成します。原案を作成し、二度・三度と読み込み、校正することで情報が整理でき、納得のいく遺言書を形作ることにつながります。
その際、調査結果を表した相続関係説明図と財産目録をもとに遺言の内容を決めるわけですが、遺言の内容は遺言をする人が自由に決めることができるのが原則です。もちろん自分以外の第三者に対して一方的なことを記載しても強制力を生じることはなく、厳密には遺言できる事項は法定されていますが、自己の財産については法律の範囲内で遺言者の意思が第一となります。
この点、場合によっては遺言書に書いていないとできないこともあります。例えば、未成年者が残される家族となることが見込まれる場合に自分の友人に我が子の面倒を託したいときは「未成年後見人の指定」を行いますが、これは遺言でなす必要があります。このような民法の専門的知識が必要な場合に、ご自身のみで作成すると漏らしてしまう可能性が高まることも自筆証書遺言のデメリットといえます。なお、同じような項目として、未成年後見監督人の指定、相続分の指定・指定の委託、遺産分割方法の指定・指定の委託、遺産分割の禁止、遺産分割における共同相続人間の担保責任の定め、遺言執行者の指定・指定の委託、遺留分が減殺された場合の受遺者又は受贈者の負担額の割合があります。
(2) 全文の自署・法的要件のチェック
繰り返しですが、自筆証書遺言は遺言をする人が「自分で」自書をしなければなりません。しつこいですが代筆はできません。以前は、本当に全文を自署する必要がありましたが、現在は前述の「財産目録」については自書でなくともよいとされています。ただし、この場合も財産目録の各ページに署名と押印が必要とされています。また、自筆の際に付添の方が手を添えて補助するこもできませんので、自書が困難な場合は自筆証書遺言ではなく「公正証書遺言」によるべきです。この全文(財産目録を除く)が自書されていることが、法的要件の1つですが、このほかのチェックポイントとして、「日付が自書されていること」、「氏名が自書されていること」、「印を押していること」、「修正の有無の確認(ある場合は法定方式に沿っているかの確認)」、「封(自書と本文に使用した印による。ただし、法務局での遺言書保管を利用する場合は無封)」があります。
なお、法的要件ではありませんが、ご紹介したとおり自筆証書遺言には信ぴょう性が低いというデメリットがありますので、これを少しでも解消するため、「印鑑は実印を用いること」、「2枚以上の遺言書には契印をすること」、「筆跡を確認できる他の文書を用意すること」、「印鑑登録証明書を用意すること」、「遺言書を書いているところを映像として残すこと」が考えられます。特に「印鑑」については、信ぴょう性を増すため「印鑑登録をした」実印であることが重要です。印鑑を複数持っていてどれが実印か不安がある場合は、印鑑登録をやり直すことをおすすめします。
遺言書の保管
せっかく遺言書を作成しても、適切に保管しなければその効果は現れません。場合によっては遺言書の存在が遺族に認識されないまま、相続財産の整理を終えられてしまう可能性すらあります。したがって、遺言書の作成と同様に、しっかりとその保管について考えなければなりません。
自筆証書遺言は、かねてから費用をかけず自分自身で作成し、保管するものとして利用されてきました。遺言内容によってはそこで定めた遺言執行者が保管することもありましたが、いずれにしてもそのデメリットは既にご紹介したとおりです。これを少しでも解消するため令和2年7月施行の遺言書保管法により法務局において遺言書を保管することができるようになりました。この制度を利用することにより、遺言書の紛失等のおそれがなくなり、相続開始後に必要な家庭裁判所による検認も不要となります。
この法務局での遺言書の保管は、遺言をする人の住所地又はその本籍地若しくはその所有する不動産の所在地を管轄する法務局(遺言書保管官)に対して申請をすることが必要です。詳細は、法務省をご覧いただければと思いますが、弊所は、この制度について、長期間の保管ができるにもかかわらず手数料も安価と考えており、利用をおすすめしているところです。
また、この制度を利用し、さらに「指定者通知」を希望することで、仮に相続人が遺言書が保管されている事実を知らない場合も、遺言者の死亡の事実を法務局(遺言書保管官)が確認した際に、遺言書が保管されている旨をお知らせすることができるようになるというメリットもあります。
以上遺言書のうち自筆証書遺言についてご紹介しましたがいかがでしたでしょうか。「自分でできる!」と思った方、「自分ひとりではちょっと・・・」と思った方、様々いらっしゃるかと思います。いずれにしても、遺言書は作ることそのものが目的ではなく、「争いごとの防止」にあることを忘れないようにすることが重要と思います。
まとめ〜自筆証書遺言が適する場合
自筆証書遺言は、自分自身で作成でき、手軽で費用が基本的にかかりません。その一方、紛失などのリスクのほか、信用性が低い、作成する際が大変で、さらには遺族に手間をかけるなどのデメリットがあります。これらを踏まえたうえで自筆証書遺言の方式に「よれなくはない」と思われる場合は、次のとおりです(総論としては公正証書遺言がベターと考えており、自筆証書遺言を積極的におすすめするわけではないため、持って回った表現をしています。)。
(自筆証書遺言に「よれなくはない」場合)
・内容が短文である場合(「すべての財産を○○に譲る」のみ)
・財産部分よりも「願い・想い」を重視している場合
・遺言書作成後に財産の変動が見込まれる場合
・定期的に更新したい場合
遺言書作成についてこちらもご覧ください(遺言書の作成)
あおき司法書士・行政書士事務所(宇土市)では、自筆証書遺言の作成サポートを行っています。まずはお気軽にご相談ください。
📞平日9:00~17:00 📞080-9267-8608
面談中など電話に出れないことがありますので、相談予約フォームのご利用をお勧めしております。