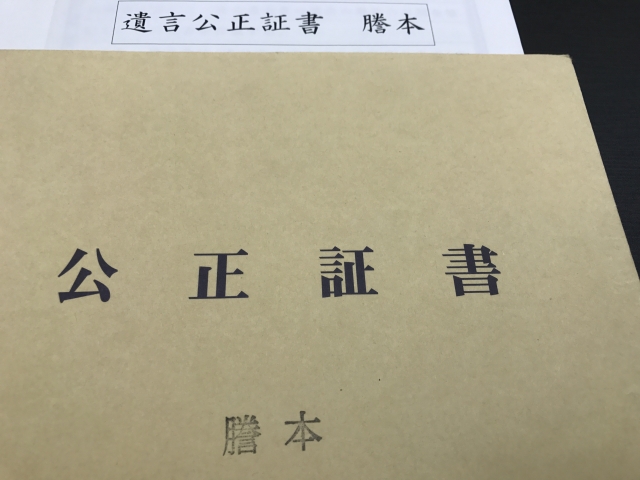遺言とは
遺言とは、一定の方式によって、その遺言をした者(遺言者)の死後の法律関係を定める最終の意思表示です。テレビドラマなどでも遺言書が見つかるシーンなどがよくありますので、どなたも遺言がどのようなものか、ある程度のイメージはできるのではないでしょうか。
ところが、実生活になると遺言書が作成されていることはいまもって多くはないようです。日本財団の2016年・遺贈に関する意識調査によると遺言の作成率はわずか3%だったとのことです。一方、家庭事件の審判などを行う家庭裁判所における相談件数は、1992年からの20年間で約3倍に増加したという実績もあることから、徐々にではありますが、遺言の必要性と有効性が認識されてきているといえます。
遺言は何のために
では、なぜ遺言が必要と認識されてきているのでしょうか。上記のとおり遺言は、遺言者の死後の法律関係を定めるものですが、それは主に財産に関するものとなります。人が亡くなると、その人の財産は相続財産として、配偶者や子などに引き継がれるのが一般的です。このことは、民法に「法定相続」として定められていますが、仮に遺言書がない場合は、原則としてこの民法に定められた法定相続分による割合で引き継がれることとなります。しかし、亡くなられた方が自身の財産について具体的な考えがある場合、例えば、「自分の介護をしてくれた長男の妻に譲りたい」、「遠くに住む長男・次男ではなく、同居してくれた三男だけに不動産を譲りたい」といった場合は、民法の定めだけでは解決することが難しくなってしまいます。このような場合に、遺族・相続人の間で円満な話合いがなされればよいのですが、残念ながら遺族・相続人の間で争い事になってしまうことも少なくありません。そこで、亡くなられた方のご自身の財産と残される家族への想いを実現する方法の一つとして、遺言は利用されています。
遺言があった方が好ましい場合
一般論として、遺言があった方がよいということはご理解いただけたと思いますが、さらに具体的に遺言書を作成しておいて方が好ましい場合(動機)として、おおきく2つ考えられます。一つは積極的に争いを防止したい場合、もう一つは今のところ心配はないけれども家族の状況からみて万全を尽くしたい場合です。少し具体例をご紹介します。
(1) 争いを防止する必要がある
再婚をした場合は、再婚相手と前妻との間の子が争うことが想定されます。また、独身で配偶者・子がいない場合は、親・兄弟姉妹あるいは甥姪が相続人となりえますが、人間関係が複雑となり相続でも争いとなる傾向があります。また、同居の家族と別居の家族がいる場合も、それまでの生活(人間)関係が相続に対する感情と入り混じり、争いとなる傾向があります。
また、離婚・再婚あるいは不倫により、それぞれの相手に子がいる場合は、死して初めて顔を見る者同士が相続人となることもあり、それまでの生い立ちが相続関係を複雑にする傾向があります。
上記のように複雑な人間関係とそれぞれの感情に、民法の規定をそのまま当てはめてしまうと、法律上問題はなくとも、不条理・不合理な結果が生じかねません。そこで、遺言者自身が考える合理的な財産配分を内容とする遺言書を作成し、関係者を納得させることで、親族間の紛争防止につなげることができます。
(2) 円満な環境を維持したい
高齢の方の中には、戦争・病気で親や配偶者を亡くされた、若くして親元を離れて就職したなど、生活そのもの、あるいは家族について大変な苦労をされた方が少なくありません。そのような方は、自分自身がした苦労を子どもにはしてほしくないという想いを持たれることが多いようです。遺言書には、「残す財産について自分が責任をもって決定するから子どもたちに争ってほしくない」という「決意」を表すことができます。
また、長年連れ添った配偶者を残す場合、自分の死後も子どもたちと仲良く暮らしてほしいという想いを表すこともできます。あまりしたくはない想像ですが、人間いざ現金など具体的な財産を目にすると人格が変わることもあります。残す財産を妻の今後の生活に使ってほしいと思っていたところ、子どもたちが法律どおりの権利を主張してしまい、妻に満足な財産を残してあげられなかったとなっては、故人の意思が尊重されないこととなってしまいます。遺言書には、このような遺言をする方の残された家族への想いを表すことができます。
上記のほか、「遺産を社会福祉に役立ててほしい」、「残してしまうペットの面倒をみてほしい」、さらには、「これまでの家族への感謝の気持ち」といった「願いや想い」を遺言書には表すことができます。
人の死は避けては通れません。それでもやはり、自分自身が亡くなった後を想像することはつらいものです。遺言書の作成は、そのようなつらい状況での作業となります。あおき司法書士・行政書士事務所(宇土市)では、お一人おひとりの想いに寄り添い、遺言書を作成する方が安心できる、そして残される方々の幸せにつながるような遺言書作成のサポートさせていただいております。
こちらもぜひご覧ください→遺言書の作成